古代海水からからの恵み『ヨウ素』
人との出会いに助けられて
幼い時代にうがい薬あるいは消毒薬として知られるヨウ素、私は赤い「ヨードチンキ」をよく覚えています。昭和時代の人はご存知ですね「赤チン」です。単純に傷口に塗ってよく効いた薬との感がありますね。15年程前、食品素材の機能製品の研究・開発のことで京都薬科大学学長の田中久博士と微量元素学会でお会いする機会があり出席していました。
先生は「今はビタミンの時代その後はミネラル、更に微量元素の時代になるから勉強したらと指導いただきました。その後、何度か学会に参加し、その後は、当会のセミナーで数階講演いただきました。その時のアドバイスがいつも頭の中にありました。
微量元素を含む製剤をいつか世に出そうと思っていました。

その縁で田中先生には私の出版本「糖鎖の健康学」の執筆も頂きました。「温故知新」は私の事業推進のモットーとしています。すでに35年事業を行ってまいりました。その後、人とのめぐりあわせで「ヨウ素製剤」をご紹介頂き、研究・開発に着手。50年ぶりに新製品として微量元素を含む製品の企画・開発・販売することになりました。
■一般社団法人免研アソシエイツ協会
医療総合プロデューサー 代表 山本英夫
ヨウ素の生成と分布
自然界には海水中や分子化合物中に一価の陰イオンを形成して存在します。結晶は光沢のある黒色個体で気体は紫色である。ヨウ素は、フッ素、塩素、臭素などのハロゲン元素の中でも工業的に非常に貴重な資源であり、また甲状腺ホルモンの構成元素で人体に必須の微量元素、微量栄養素である。
■1. ヨウ素の発見
ヨウ素は生物の中から新元素が発見された希有な例である。19世紀初頭のフランスはナポレオン戦争の頃で大量の火薬を必要としていた。1811年、フランスの化学者クールトアは火薬の原料となる硝石の製造の際、海藻灰に硫酸を加えすぎたことから、ヨウ素が蒸発して紫色の上気蒸気となり結晶となることを発見した。
■2. ヨウ素の生成と分布
誕生時の地球は高温であったため、ヨウ素は地球内部(マントル)から塩素などとともに脱ガスにより多くが大気中に放出され、40数億年前に海が誕生した時は、そのほとんどが原始海水中に溶け込みヨウ化イオンとして安定して存在していた。27億年ほど前に光合成が始まり、有機物が海底に堆積するに伴い、ヨウ素も海底堆積物に取り込まれ海水中のヨウ素濃度は大幅に低下したと考えられる。ヨウ素の総量の70%は海底表層の堆積物の中に含まれていると推測されている。

ヨウ素の作り方の変遷
ヨウ素はこれまでに海藻、石油かん水、天然ガスかん水を原料として、様々な方法で製造されてきた。ヨウ素がデンプンに包接されることは、ヨウ素デンプン反応として広く知られています。デンプン法は活性炭の代わりにデンプンにヨウ素を吸着させるもので、古くから旧ソ連で行われていました。日本でも1925年ごろ、一時的に行われていた方法です。ヨウ素遊離にかん水に、遊離ヨウ素量の約120〜150倍のデンプンを投入します。吸着されたヨウ素は、水あるいは亜硫酸水素ナトリウムで抽出します。
■3. 日本は世界第二位のヨウ素生産国
生産量はチリについで第二位を誇るヨウ素産出国です。日本では、天然ガスとともに汲みあげられる地下かん水に含まれるヨウ化ナトリウムからヨウ素が製造されます。ヨウ素は、1811年にフランスで海藻の焼却灰から発見されました。いまだに化学者の中にもヨウ素は海藻から製造されていると考えている人がいますが、実はヨウ素は、地下かん水あるいはチリ硝石から生産される大地の恵みなのです。
■4.天然ガスとともに採れるヨウ素
日本の主な水溶性天然ガス鉱床は、地域的には、新潟県、千葉県、宮崎県、沖縄県等に分布しています。この地層水は、「かん水」と呼ばれ、古代海水が地層の中に閉じ込められたものです。その成分は、現在の海水とよく似ていますが、現在の海水に比べて約2000倍の約100mg/lのヨウ化イオンを含むこと、硫酸イオンが少ないことなどにオ大きな特長があります。ヨウ素の起源は、古代に海底に堆積した動植物の遺骸あるいはヨウ素を蓄積した藻類と考えられます。

■5. 古代海水からヨウ素を取り出す
地下500m〜2000mから汲みあげられたかん水(古代海水)は、天然ガスを分離した後、ヨウ素の製造工程に送られます。かん水中のヨウ素の取り出しには、現在は、ブローアウト法とイオン交換樹脂法の二つの方法が採用されています。現在、国内・海外のメーカーのほとんどが、ブローアウト法を採用しています。
■6.天然ガスとともに採れるヨウ素
日本の主な水溶性天然ガス鉱床は、地域的には、新潟県、千葉県、宮崎県、沖縄県等に分布しています。この地層水は、「かん水」と呼ばれ、古代海水が地層の中に閉じ込められたものです。その成分は、現在の海水とよく似ていますが、現在の海水に比べて約2000倍の約100mg/lのヨウ化イオンを含むこと、硫酸イオンが少ないことなどにオ大きな特長があります。ヨウ素の起源は、古代に海底に堆積した動植物の遺骸あるいはヨウ素を蓄積した藻類と考えられます。
■7.ヨウ素はリサイクルされる
日本では、ヨウ素は、天然ガスとともに汲みあげられる地下かん水から製造されます。しかし、かん水の汲みあげによる地盤沈下への配慮から汲みあげ量が制限されています。ヨウ素資源は限られています。回収率の高い事例として偏光フィルムとX線造影剤の回収液があります。無機ヨウ素は電気透析で抽出・濃縮できます。又、有機ヨウ素は高温分解し無機ヨウ素として回収しています。
ヨウ素の歴史
ヨウ素の効能は古くから知られていた?
昔から海のない山間地域では、甲状腺肥大(甲状腺腫)が多く発生し、その治療に海藻が有効なことで知られていました。海藻のさまざまな医学的な効能は、紀元前2000年頃の中国最古の医書「神農本草経」に掲載されています。なかでも褐藻ホンダワラ類と考えられる海藻が甲状腺腫を代表とする腫瘍を治すなどの記述が確認されています。ホンダワラは温帯から熱帯にかけて広く分布する海藻で、海藻のなかでも最も進化したものと言われます。
※神農・・中国古代伝説上の薬の神。たくさんの植物をなめて、薬物を見分けたとされる。
一方、ヨーロッパでも10世紀頃からアルプスの山中には甲状腺が肥大した人がいることが分かっています。中世のヨーロッパでは甲状腺腫の治療にいろいろなものが使われていましたが、13世紀になって、特にその一つとして海綿の灰が甲状腺腫の治療に使われていたようです。しかし、その有効成分がヨウ素であることが明らかになったのは、19世紀に入ってからです。
1811年にフランス人化学者のクールトアによってヨウ素が発見されて間もなく、1820年にはスイス、ジュネーブの医師コワンデが初めてヨウ素を医療に用いました。彼はヨウ化カリウムとヨウ素のアルコール溶液(ヨードチンキ)をつくり、甲状腺腫の治療に卓効を期待すると述べています。彼の考え方は正しかったのですが、ヨードチンキを服用させられた患者は、粘膜ら対する刺激作用のため激しい胃痛に苦しみ、この治療法は広まりませんでした。
その後、ヨウ素は脊椎動物にとって重要な元素で、甲状腺ホルモンの成分として代謝の調節を担っていることが明らかになってきました。20世紀に入ると、ヨウ化カリウムがクレチン症や甲状腺腫の治療に広くつかれるようになりました。
ヨウ素は地球を駆け巡る・・・ヨウ素の大気循環
地球上のヨウ素は、海水や土壌、大気中に分布していますが、その大部分が海水中に存在します。しかし、ヨウ素は、海水中に止まっている訳ではありません。実は、ヨウ素は、地球規模で岩石圏、水圏、大気圏を循環しています。ヨウ素の揮発は、海洋から陸圏へヨウ素を供給する人類を含めた陸圏の脊椎動物の生命維持に不可欠なプロセスと言えます。

その後の研究により、水田や泥炭地など陸圏環境かせのもヨウ素が揮発していることも解っています。特にイネ・稲はヨウ化メチルを大気中に送り出す機能がふり、これだけで大気中のヨウ素の4%ほどが供給されています。地球規模のヨウ素の年間総揮発量は、およそ30〜40万トンと見積られています。
うがい薬に使われるヨウ素
ポビドンヨード(代表ブランド「イソジン」)は、殺菌力はもちろんのこと、即効性にも優れていることから、うがい薬や手指の殺菌、傷の消毒薬などに広く使われている代表的な消毒薬です。ヨウ素の作用機序に関する仮説はいくつかありますが、ヨウ素と水と反応して生成するH2OI+が細菌およびウイルスの表面の膜タンパクに直接働くことにより殺菌・消毒作用を示すと言われています。
『ポビドンヨードの効力に着目したアメリカ航空宇宙局(NASA)は、19639年夏、宇宙船アポロ11号が人類初の月面着陸を成し遂げて太平洋上に着水した際、地球外の未知の世界から運んでいるかも知れない細菌の洗浄・消毒にポビドンヨードが有効と判断し、更に海洋に対する汚染への配慮からポビドンヨードの殺菌消毒剤を船体に注ぎかけ洗浄・殺菌したという秘話があります。』
ヨウ素は人間や動物の必須元素
生体必須微量元素の一つとして人や動物の生存、成長に欠かせないのがヨウ素です。ヨウ素は体内に約20〜30mg位は存在します。1日0.014.〜0.033mgが必要量とされ、身体の中のヨウ素の半分があごの下(頸部)にある甲状腺に集まり、甲状腺ホルモンのチロキシンとトリヨードチロニンを作る材料になります。
これらのホルモンは、交感神経を刺激して、タンパク質や脂質の代謝を促進します。甲状腺ホルモンが不足すると、新陳代謝が悪くなったり、体力低下、成長障害、精神発達の遅れなどが生じ、妊娠中の女性は特にヨウ素不足は注意が必要です。
■参照書籍「ヨウ素の本」等々より
■1. 日本人におけるヨウ素摂取基準
2010年から変更された成人の推奨量が150μg/日〜130μg/日になった。日本人ではヨウ素の摂取量は食事摂取基準推奨量よりも、かなり多いと考えられる、不足がおこる可能性は限りなくゼロに近く、過剰摂取に注意となっている。間欠的(一定の時間を於いて摂取ができたりできなかったりすること)な高ヨウ素摂取(昆布由来製品3〜5mg/日)と記載されています。ヨウ素については未だに栄養摂取量の算出の対象になっていない。その理由は不明であるが、食品中のヨウ素含有量についてのデータが不十分なことが一つの要因ではないかと推測される。
■2. 世界ではヨウ素欠乏症多々
日本以外の国においては「ヨウ素」という言葉から連想するのは、「ヨウ素欠乏症」であると言っても過言ではない。現在においてもヨウ素欠乏症は世界中で公衆衛生上の大きな問題であり、ビタミンA欠乏症、鉄欠乏症とともに世界の三大微量栄養素欠乏とされる。
2.胎児、新生児、乳児のヨウ素欠乏症・・・
ヨウ素欠乏症による精神発達遅滞は唯一の予防可能な精神発達障害である。ヨウ素欠乏症は、それが起こった時期、すなわち胎児期、新生児期、成人によって、またヨウ素欠乏の程度によって非常に多彩な症状を示す。特に重要なのは中枢神経系の発達に甲状腺ホルモンが必須な胎児、新生児、乳児でのヨウ素欠乏症である。またヨウ素欠乏状態では放射性ヨウ素に対する甲状腺の被爆量がすべて年齢に於いて増加することが知られている。
3.妊婦、授乳婦、小児のヨウ素欠乏症・・・
近年、問題となっているのは妊婦、授乳婦、乳児、若年小児におけるヨウ素欠乏症である。
WHO、ユニセフ、ICCIDDはヨウ素欠乏症における妊婦、授乳婦へのヨウ素補充を支持してきました。
◆世界のヨウ素欠乏症対策と国際協力・・・
世界のヨウ素欠乏を根絶するために1985年ユニセフ、WHO<オーストラリア政府などの支援によりヨード欠乏症国際対策機構が創設された。
■国立成育医療研究センター資料より
有機ヨードについて
有機性ヨードは、1921年に薬学大家 故牧野民蔵・千代蔵の両先生が「ヨウ素(ヨード)は、甲状腺ホルモンに含まれ免疫機能を高める成分である事」に着目して製造されたのが始まりです。また、ヨードが放射性被爆者に有効であることから有機性ヨードは広島・長崎の原爆被爆者の治療に利用され大変喜ばれたそうです。
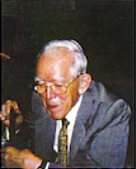
その後、聖マリアンナ医科大の飯島登名誉教授(92歳で亡くなられた)
が30年臨床研究され生活習慣病の治療に成果をあげられています。
【ヨウ素素材開発者】
元・聖マリアンナ医科大学名誉教授
医学博士 飯島 登先生(東大医学部卒)
